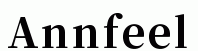肩こり・首こりとは
一般的にこのように書かれています。
参考
肩こりとは症候名のひとつ。肩だけでなく首も凝ることが多い。「肩が張る」とも言う。
主に僧帽筋に起こる症状。多くの方が自覚している症状でもある。
肩こり・首こりの原因は?
このように書かれています。
1. 長時間同じ姿勢でいること
長時間同じ姿勢でいることで起こる筋肉の疲労です。
デスクワークや読書などで長時間同じ姿勢を続けると、首から肩の筋肉が硬直し、血行不良から肩こりを引き起こします。
特に最近増えているのが、PCやスマホを長時間使用することで起こる肩こりです。PCやスマホの操作をするとき、首を少し前に突き出して両肩をすぼめる姿勢になり、同じ筋肉に負担をかけてしまいます。
2. PC・スマホの見すぎによる目の疲れ
PCやスマホを長時間使用することで生じる目の疲れも、肩こりの原因になります。
細かい文字を見続けると、目やその周辺の筋肉が緊張します。特にPCやスマホは光源を見つめているのと同じなので、目が常に緊張を強いられている状態です。
まばたきの回数が減ることからドライアイになりやすく、眼精疲労を引き起こします。
眼精疲労が蓄積すると不快感が脳に伝わり、首や肩の筋肉が硬直するため、肩こりが慢性化してしまう可能性があります。
3.ストレス
時間に追われて生活する現代社会では、肉体だけではなく精神的なストレスを抱えている人も多いことでしょう。そんなストレスも肩こりの原因のひとつです。
精神的なストレスから身体の機能を管理する自律神経が乱れ、血流が悪くなったり筋肉が硬直したりすることがあります。特に首周りや肩の筋肉が硬くなりやすいので、なるべくストレスをためないようにしましょう。
4. 運動不足
運動不足が続くと肩こりを引き起こす可能性があります。
運動不足になると筋肉量が減り、筋力が弱くなってしまいます。弱くなった筋力を支えるために筋肉が緊張状態になり、肩こりの原因になるのです。
また、筋力が弱くなることで血行不良が起こり、酸素や栄養分が伝わりにくくなることから疲労を感じやすくなります。適度な運動で筋肉量の低下を防ぎ、柔軟性を高めてしなやかな筋肉を保つことが大切です。運動を継続することで血流を改善し、日頃から肩こりを起こしにくい体をつくりましょう。
5. 体の冷え
体の冷えも肩こりの原因のひとつです。体が冷えて動かしにくくなると全身の血流が悪化し、肩こりが起こりやすくなります。
体が冷えると体温バランスを整えようとするために自律神経が乱れ、血行不良や筋肉の硬直につながります。気温が低い冬場だけではなく、夏場の冷房による冷えからも体を守りましょう。
また、筋肉量が少ないと体のポンプ機能が弱くなり、血液が循環しにくくなることから体が冷えやすくなります。適度な運動を取り入れて筋肉量を保つことが大切です。
肩こり・首こりの治療は?
1. 体を動かす
2. 肩や首を温める
3. 肩や首のマッサージをする
4. 肩こり解消グッズを活用する
「ツボ押しグッズ」や、患部を温める「温熱シート」「磁気アイテム」「温熱式マッサージ機」「首まくら」など
5. 薬や病院での治療を受ける|保険適用のケースも
医療機関を受診する際は、以下の2つの症状を目安にしてください。
-
- 症状が左右どちらかに偏っていて広範囲にわたる場合
- 頭痛や吐き気、しびれなど肩こり以外の症状を伴う場合
日常生活でやってほしいこと
上記が一般的に調べたら書かれていることです。
なぜ肩や首が凝るのか、痛くなるのか。
簡単に言うと「よく使っている」からです。
以上です。それしかありません。
肩や首が「悪い」わけではなく
「働き者」だということです。
よく働くから、よく使うから疲れてしまっているだけで
ということは、全然働かないところがある。ということでもあります。
働かないところがあるから肩首が「頑張ってくれている」のです。
肩首に感謝しなければいけませんね(笑)
肩首をよく使うということは
「下半身」がうまく使えていない。ということでもあります。
「地に足がついていない」とも言えます。
土台がどっしりしていると上半身は楽にいれるのです。
そこで
お勧めのワークを1つ紹介します。
足の裏・重心を意識してみよう
①楽に立ちます。
②左右の足を前・後ろ・右・左と四分割する意識をします。
③一番体重がかかっているところはどこですか?
(右足はここ、左足はここと感じてみましょう)
④2番目、3番目、4番目と順番を左右でつけてみましょう
⑤一番意識がなかったところに軽く体重をかけてみます
(左右行いましょう)
⑥その後また楽に立ち、最初との違いを感じます。
足がついた感じがしませんか?
足がついていると肩や首の力が抜けてくるのを感じるかと思います。
毎日の習慣としてぜひやってみてくださいね!!