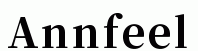子宮内膜症とは
一般的にこのように書かれています。
子宮内膜症とは
子宮内膜症とは、子宮内膜が子宮の外側(例えば卵巣や腹膜など)の異常な部位で発生し、成長する病気の事。
これにより卵巣にチョコレート色の血液を溜めこむ卵巣チョコレート嚢胞が形成されることがあります。
腹膜に発生すると卵巣や欄干、腸の癒着が起こり、不妊の原因になることもあります。
月経のある女性の約7~10%に発生し、特に20~30代女性に多く見られます。
症状には
・月経痛が強い、痛み止めが効かない
・月経痛が年々悪化している
・月経時以外の腹痛がある
・性交時に腰を引いてしまうほどの痛みがある
・排便時に痛みがある、肛門の奥が痛い
・血尿、血便がある
・妊娠を希望しているが、なかなか叶わない 等
子宮内膜の治療は?
薬物療法と手術療法があります。
薬物療法
①痛みを抑えるための対症療法
→消炎鎮痛剤を使用。症状は抑えられますが、進行を防ぐ効果はありません。
②子宮内膜症の悪化を防ぎ、病変を縮小させるホルモン療法
→基本的に生理が来るたびに症状が進行するため、生理サイクルをコントロールしたり、生理量を減らすことが有効となるそうです。
生理をコントロールする事で、結果的に生理量が減って生理痛が軽減します。
・低用量ピル(LEP)
・ミレーナ(子宮内黄体ホルモン放出システム)
医師によって、子宮内にミレーナを装着します。子宮内に挿入するので、妊娠・出産経験がある女性が主な対象者になります。
挿入後は、黄体ホルモンが子宮内で持続的に放出されます。ほぼ確実な避妊にもなり、一度挿入すると、5年間有効です。
・ジェノゲスト(黄体ホルモン製剤)
一番新しい治療薬。
エストロゲンを低下させないので、更年期障害や骨粗しょう症などの副作用は心配ありませんが黄体ホルモンの副作用が出ます。
副作用としては、不正出血、頭痛、倦怠感、気分の落ち込み、乳房痛などがあります。
特に不正出血がよく見られます。
・GnRHアゴニスト
点鼻薬と注射があります。とても効果的ですが、副作用もあり、特に骨粗しょう症リスクが上がるため、最長で6ヶ月までしか使用できません。
子宮内膜症を小さくしてから摘出するために、手術前に使用することもよく行われています。
手術療法
手術には開腹手術と腹腔鏡手術に大別されますが、近年は低侵襲の腹腔鏡手術が選択されるケースがほとんどです。
どちらも病変部を切除することには変わりありませんが
将来的な妊娠を希望していない場合には、再発のリスクをより低くするため、子宮・卵巣・卵管も切除することがあります。
薬を使わず何とかしたい
どの症例もそうですが
「必要だからその症状が出ている」のです。
子宮内膜は子宮内にだけあればいいもののほかのところにも作らなければならなくなった。
子宮内の様子がおかしくなっているのは確かですね。
子宮内膜症は痛みが強いのも特徴でもあります。
月経がはじまったら辛さしかない!!と思うことも多いと思います。
そこで
月経ではないときの過ごし方にフォーカスしてみましょう。
月経困難症のページも参照してください。
・地に足がついていること。
・骨盤周りの血流か良好なこと。
この2つに注意してみましょう。
地に足がついている
基本中の基本なのでこれは押さえておいてください。
立っているとき、座っているとき、足が地にはついていると思いますが
「床を感じる」ことができていますか??
そこからの姿勢維持です。
家でいうと足裏が基礎です。土台です。
その上に建物が乗ると想像し、その建物が体です。
これはとても大切なことです。
足裏で体をしっかり支えられているでしょうか?
耐震は十分ですか?(笑)
骨盤周りの血流が良好であるために
骨盤が良く動いていたいなと思います。
それも
力づくで動かすのではなく、骨盤を「転がす」ことをやってほしいと思います。
仰向けになって両膝を立て足裏を床につけます。
お尻が床についていると思うので、そのお尻をころころと転がします。
恥骨が床に近づいたり(骨盤前傾)
恥骨が床から離れたり(骨盤後傾)
骨盤の前後傾の動きをお尻を床に転がしながら行います。
骨盤が動いてくると股間節も動きますよね?
これを
仰向けでも、椅子に座ってでもできると思うのでぜひ気づいたときにやってみてほしいなと思います。
足からの床反力と骨盤の動きで動きをつなげていくと下半身の流れが良くなっていくと思います。
是非やってみて下さいね。