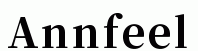子宮脱とは
一般的にこのように書かれています。
子宮脱とは
「子宮脱」とは、その名のとおり「子宮が腟から脱する(出る)」状態をいいます。
何らかの理由で、子宮が本来の位置よりも下がり、腟内に出るものを「子宮下垂」、それがさらにひどくなり、子宮の一部または全部が腟の外に出てしまった状態を「子宮脱」といいます。
子宮脱の原因は?
このように書かれています。
子宮脱は、子宮や膀胱、直腸など骨盤内の臓器を支える「骨盤底」が、弱まったり傷ついたりすることによって起こります。
子宮脱の主な原因の一つは、妊娠・出産で子宮を支える筋膜や靭帯が緩むことです。
経腟分娩(自然分娩)の場合、胎児がママの腟を通るときに骨盤底が傷つくことがあり、年齢を重ねるごとにその緩みが大きくなってしまうのです。
そのほか、肥満や、排便のいきみ、慢性的な咳、継続的に重いものを持つ仕事など、腹圧がかかりすぎることが子宮脱の原因になることもあれば、
加齢や閉経により女性ホルモン(エストロゲン)減少の影響もあり骨盤底の組織の弾力が弱まることも原因の1つと考えられています。
子宮脱の治療は?
このように書かれています。
ペッサリー(リング)の挿入
初期の子宮脱だったり、持病などで手術ができなかったりする場合は、「ペッサリー(リング)」というドーナツ状の器具を腟の中に挿入し、子宮を元の位置に固定します。
長期間ペッサリーを挿入したままにしておくと、炎症を起こしたり、おりものが増加して出血したりすることがあるので、病院で定期的にペッサリーを交換してもらう必要があります。
手術
子宮脱の症状が重く、ペッサリーでは対応ができない場合には、手術を行います。
腟から子宮を摘出し、腟などを支える筋膜や靭帯を補強する手術が「腟式子宮全摘術」が一般的です。開腹はせず、腟から器具を入れて手術を行うので、目立つ傷は残らず、体への負担はそれほど大きくない手術といえます。
最近では、子宮を温存し、腟壁と膀胱の間にメッシュを入れて臓器を支える「経腟メッシュ手術」も普及してきています。
骨盤底筋体操
家のソファで休んでいるときや、電車で立っているときなど、日常生活の中で気づいたときに次の3つの動作を繰り返してみましょう。
1. 肛門と腟を上に引っ張るように、お尻の穴を締める
2. 締めた状態で5つゆっくり数える
3. 力を抜いてまた締め直す
肥満を改善する
腹圧がかかることで子宮脱が悪化することがあるので、太り気味の人は適度な食事と運動をすることで、肥満を改善しましょう。
ただし、運動しているときなどに子宮が下がってきている感覚があれば、無理して続けず、医師に相談してください。
便秘・咳を改善する
便秘により排便のときにいきみすぎたり、喘息などで慢性的に咳をしていたりすると、腹圧がかかって子宮脱が進んでしまう恐れがあります。
食生活を改善する、必要であれば薬で治療するなどして、便秘や咳を改善しましょう。
日常生活でやってほしいこと
上記が一般的に調べたら書かれていることです。
内臓が出てきてしまうということはどういうことなのか。
切迫早産ケアでも書きましたが
上からの圧力が強すぎるのか、下の支えが弱すぎるのか、その両方か。
何も骨盤底筋だけの問題ではないと思うのです。
膣トラブルでも書きましたが
「地に足を付ける」ことはとても大切です。
下の支えの強化になるからです。
是非これは意識していただきたい。
足裏のワーク
いらない割りばしを用意いただいて
割りばしを親指側のラインで踏んでいきます
要は足で言うと内側のラインです。
次に薬指のラインに置き踏んでいきます。
小指ではなく薬指にしてください。
これが足の外側のラインです。
踏んだ後床に両足を付けるとフィット感がまずと思います。
是非やってみてください。
そして、上からの圧が強いのは切迫早産ケアでも書きました。
上半身の硬さ、胸の硬さ、胸腔の余裕が少なく固めてしまっているような動きをされている可能性があります。
仰向け、うつ伏せ、横向き、色々な寝方で
大きく胸に息を吸い、は~と息を吐く。
胸をよく動かしてください。
また、仰向けで横になり両手を前ならえするように天井に伸ばします。
肩甲骨は床についている状態から
片方ずつ手を交互に天井に近づけていくうごきをしましょう。
トントンと肩甲骨が足ふみするように動くと思います。
その時、胸は楽にしていてください。
もういいかな~と感覚的に思ったところで
(たくさんやればいいというものえではないです)
休憩します。
背中の感覚、胸の感覚を確認すると少し緩んでいるのがわかるのではないでしょうか?
難しいことは必要ありません。
是非やってみてくださいね。